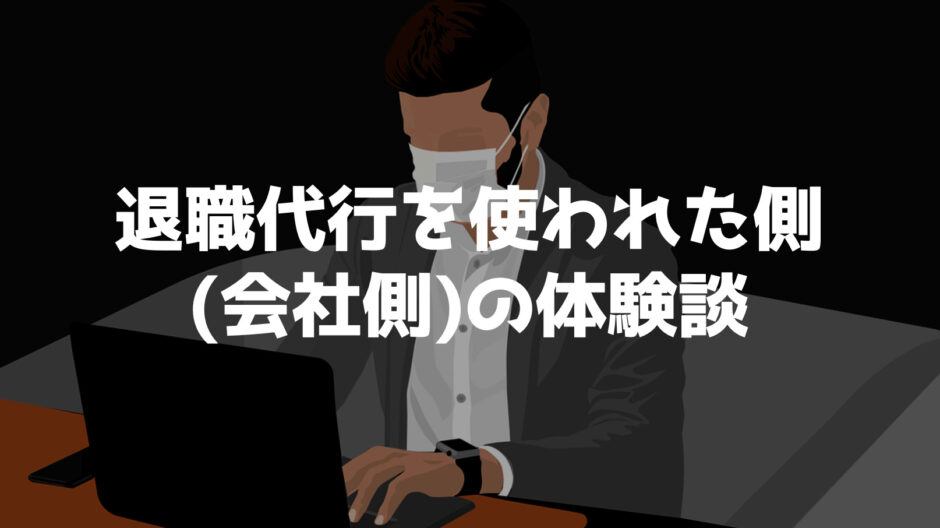「会社の従業員に退職代行を使われてしまった」「いきなり辞めて迷惑」などと驚いていませんか。
ここ数年で利用者が増加している退職代行サービスですが、実は使われた側の声も大きくなってきています。
そこでこの記事では、
- 退職代行をされた側の体験談
- 使われた際の会社側(企業側)の対応はどうすれば良いのか
以下の記事もチェック!
今月の最新情報は「【最新版】退職代行おすすめランキング20社比較!料金相場・人気業者を大公開」をチェック
目次
迷惑!退職代行を使われた会社側(企業側)の体験談|対応は?

退職代行を使われた側はどのような状況なのでしょうか。
まずは、実際の会社側(企業側)の体験談を見ていきましょう。
- 「退職代行そのものに憤慨している様子」
- 「いつから悩んでいたか気づけなかった」
- 「退職代行で社内騒然となった」
- 「辞めるなら仕事片付けていけ」
- 「社内HPに忠告されていた」
- 「明らかにこっちの非な気がしてきた」
使われた体験談1「退職代行そのものに憤慨している様子」
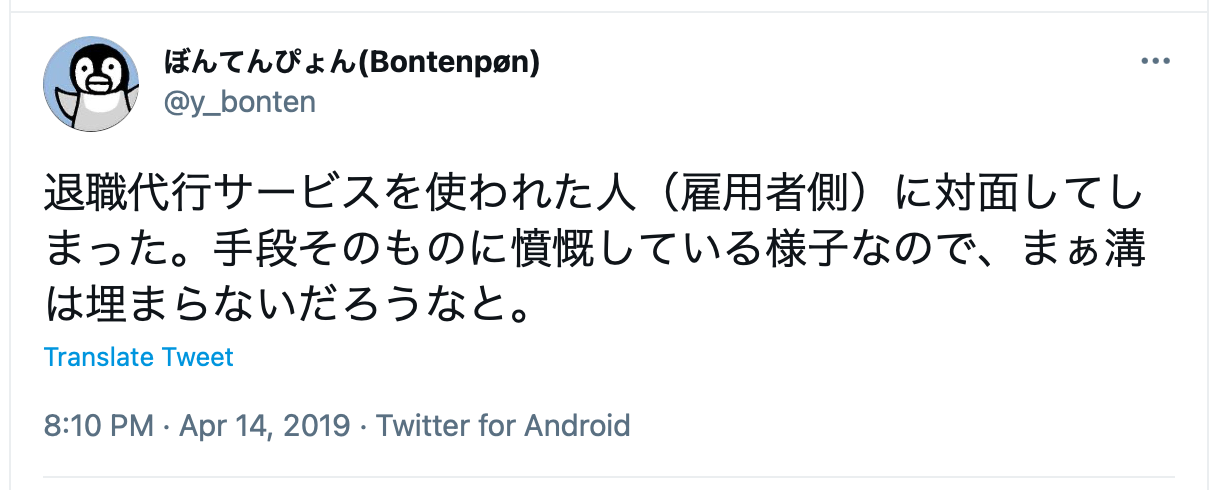
1つ目に、退職代行に対して「手段そのものに憤慨している様子」と雇用者側に対面した方の体験談です。
この方自身は雇用者側ではありませんが、退職代行サービスに納得いっていないのが伝わりますね。
使われた体験談2「いつから悩んでいたか気づけなかった」
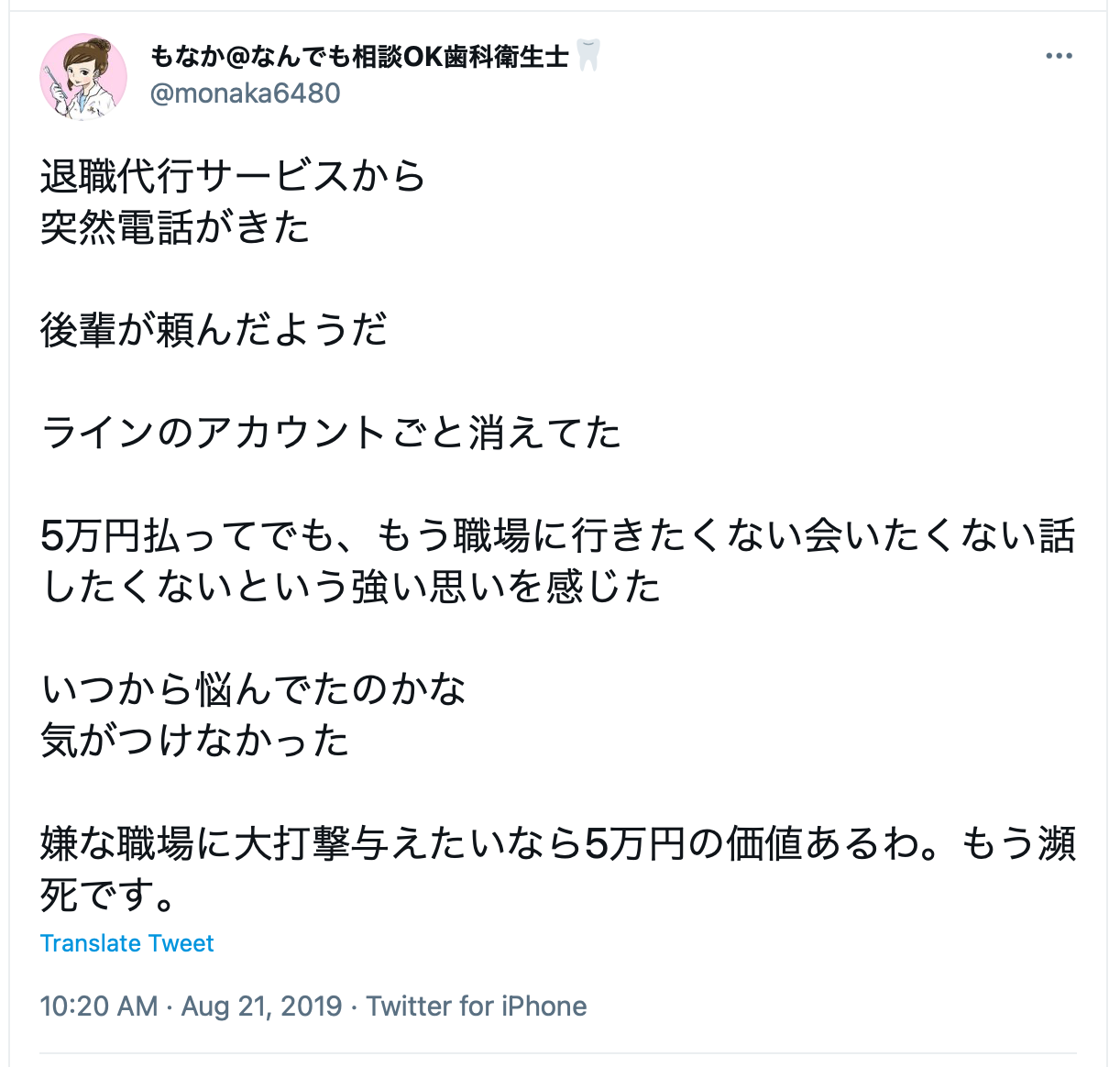
一方で、「いつから悩んでいたのかな 気がつけなかった」との声も。
このようにむしろ同情する声もあり、反応はさまざまなようです。
使われた体験談3「退職代行で社内騒然となった」

3つ目に「突然辞めた新人さんがいて社内騒然となりました」との体験談です。
この声は最も見受けられ、やはり驚きの声が多いようですね。
以下の記事もチェック!
今月の最新情報は「【最新版】退職代行おすすめランキング20社比較!料金相場・人気業者を大公開」をチェック
使われた体験談4「辞めるなら仕事片付けていけ」
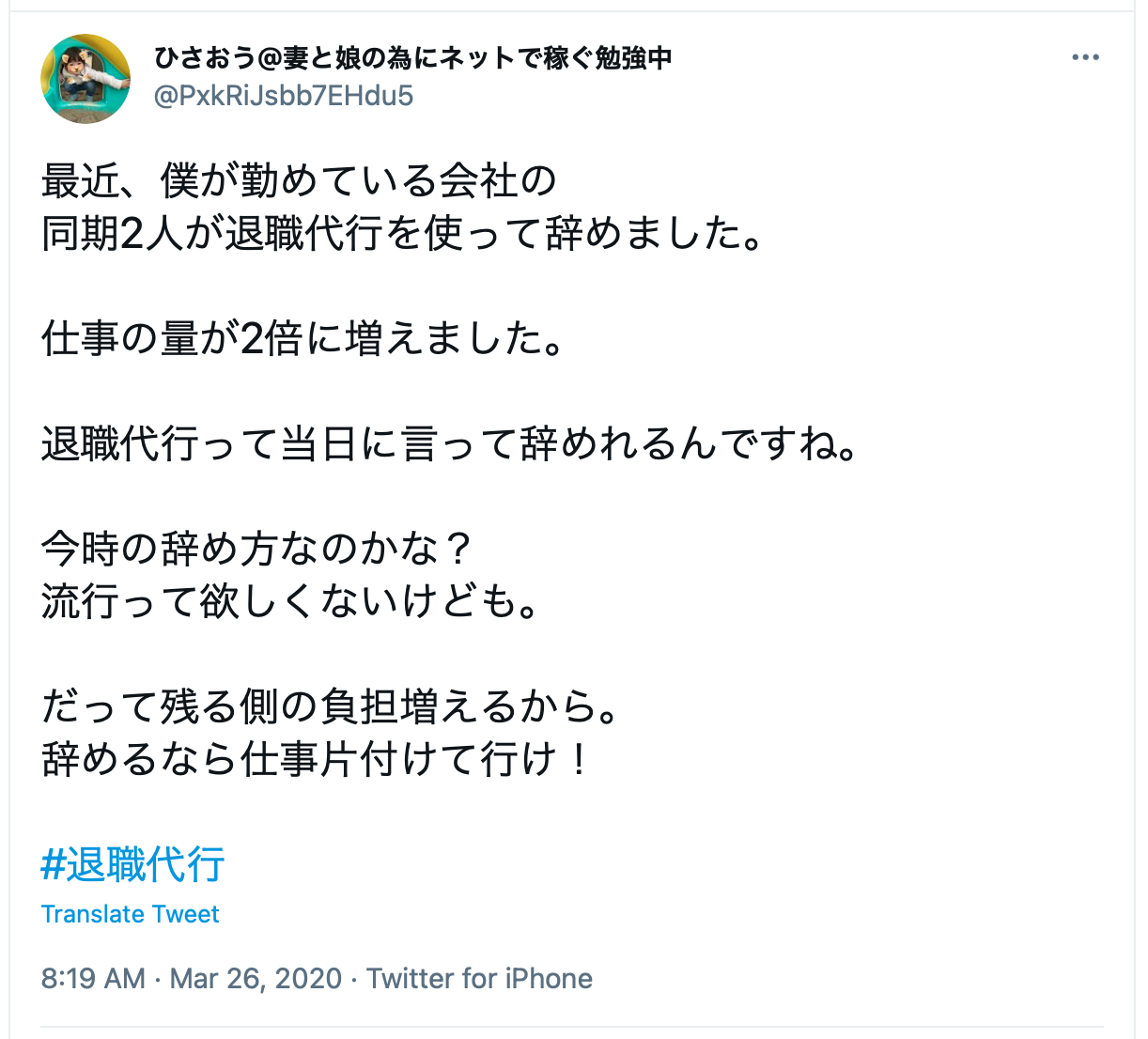
また、「辞めるなら仕事片付けていけ!」と辛辣な声も。
特に引き継ぎなどがないと残された側は負担が大きくなってしまうため、ある程度引き継ぎをしておくと良いかもしれません。
使われた体験談5「社内HPに忠告されていた」
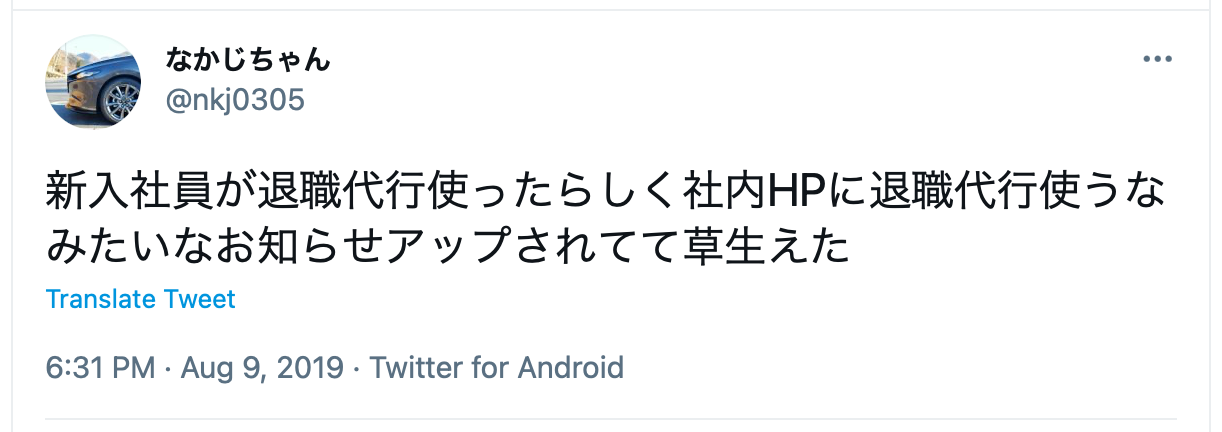
5つ目に、「社内HPに退職代行使うなみたいなお知らせがアップされてた」との体験談もありました。
企業によって反応が多様なのが分かりますね。
使われた体験談6「明らかにこっちの非な気がしてきた」
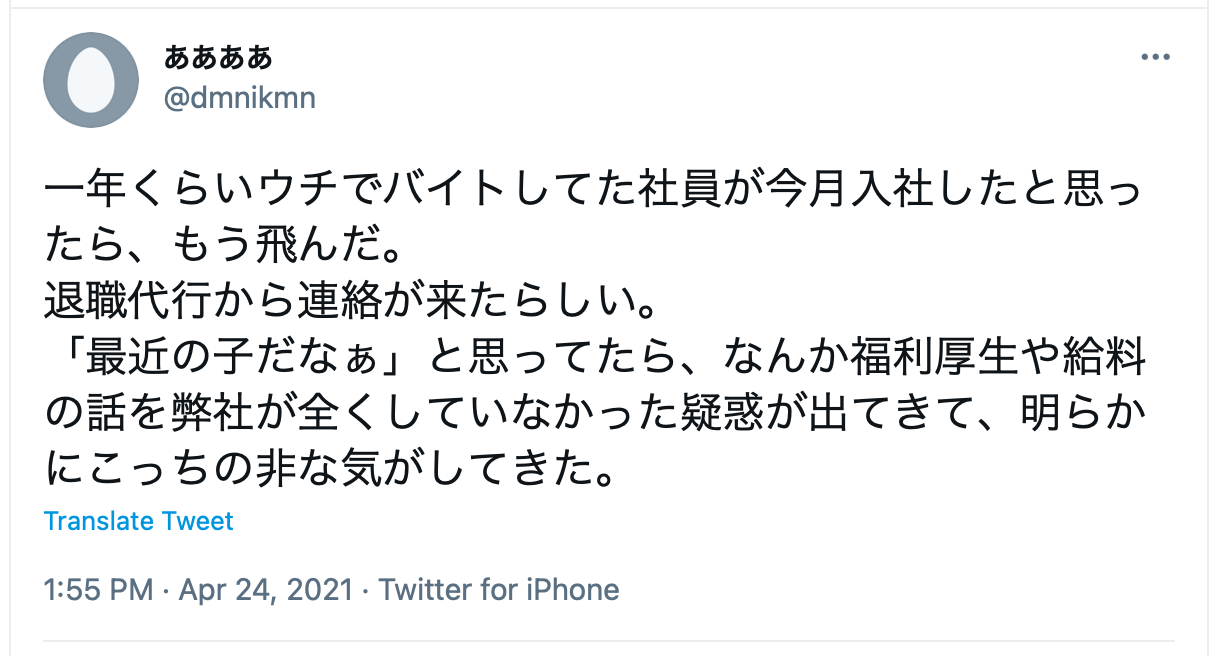
一方で「福利厚生や給料の話を弊社が全くしていなかった疑惑が出てきて、明らかにこっちの非な気がしてきた」との口コミも。
このように必ずしも労働者側だけの原因ではなく、会社側にも責任がある可能性もあるでしょう。
どのように労働者の雇用を守れば良いのか、会社側としても今一度見直してみるのも良いきっかけかもしれません。
\ 最新情報を今すぐチェック /
※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。
会社・企業側が退職代行を使われた際の対応は?5つの疑問を解説

それではもし会社や企業が退職代行を使われた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
ここからは、気になる5つの疑問について解説していきます。
- 退職は認めざるを得ないのか?
- 損害賠償を請求することはできるのか?
- 懲役解雇することはできるのか?
- 有給消化はどうすべきか?
- 未払い賃金はどうすべきか?
疑問1.退職代行は認めざるを得ないのか?
まず第一に気になるのが「退職代行は認めざるを得ないのか」という疑問です。
結論から言うと、退職は労働者一人一人にある権利であり、退職代行の行為自体は認めざるを得ません。
つまり、退職するかしないかの判断は労働者本人の自由であり、会社の許可は必要ないわけです。
この退職の自由については民放627条1項で規定されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
ー 民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)627条1項
すなわち一般的な正社員やアルバイトは、2週間前に辞職意思を伝えればいつでも、またいかなる理由でも退職できるいうことですね。
\ 最新情報を今すぐチェック /
※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。
疑問2.損害賠償を請求することはできるのか?
また退職代行を使われたことで、以下のような理由から損害賠償を検討する雇用主もいるでしょう。
- 前触れもなく突然退職された
- 引き継ぎをせずに退職された
- 人手不足にも関わらず退職された
しかし、このような理由だけで損害賠償を請求することは出来ません。
たとえ損害賠償を請求した場合でも、退職という行為に対して請求が認められることは一切なく、むしろ会社側の損害賠償請求の方が不当と判決が下されるためです。
 オトシゴくん
オトシゴくん
一方で「期間の定めがある雇用契約の会社員やアルバイト」は原則として期間中に退職できません。
もし“雇用契約”をしている労働者が、一方的に退職することで会社に損害を与えた場合は、会社側の損害賠償請求が認められるケースも。
実際に民法628条でその内容が明記されています。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
ー 民法(やむを得ない事由による雇用の解除)628条
ただし、雇用契約であっても、以下のいずれかに当てはまる場合は労働者本人の退職が優先されます。
- 契約期間の初日から1年以後に退職した場合
- “やむを得ない事情”があり退職した場合
この”やむを得ない事由”ですが、「本人の病気」「家族の健康状態や介護」「パワハラ・セクハラ」「給料未払い」「嫌がらせ・いじめなどの就業環境」などの理由で認められるケースが多いです。
以上の内容から、退職という理由だけで損害賠償を請求することは非常にハードルが高く、非現実的と言えるでしょう。
\ 最新情報を今すぐチェック /
※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。
疑問3.懲役解雇することはできるのか?
次に「懲役解雇を下すことは認められるのか」についてですが、こちらも同様ほとんど不可能です。
懲役解雇を下すのは一定の条件があり、会社が恣意的にできるものではないためです。
ただし、無断欠勤が2週間以上続いた場合は懲役解雇が認められる可能性が高くなります。
▼懲役解雇が認められる6ケース
・窃盗や横領、傷害など、刑法犯に該当する行為があった場合。
・賭博などによって職場規律や風紀を乱し他の労働者に悪影響を及ぼす場合。
・当該業務に必要となる資格や免許を有していないなどの経歴詐称。
・正当な理由なく2週間以上の無断欠勤して出勤の督促にも応じない場合。
・遅刻や中退が著しく、再三の注意や処分によっても改善されない場合。
・他の事業所へ転職をし、労務を行なえない場合。引用:http://www.roudou110.com/kiso/14.html
とはいえ、一般的には退職代行サービスを使うと退職までの2週間は有給休暇を使うため、無断欠勤扱いにはなりません。
また、もし退職者に有給休暇が足りない場合でも、自ら申告する事で病欠または欠勤扱いとして対応される可能性もあります。
さらに懲役解雇を下すためには以下3つの条件が必須です。
- 労働者が退職までの2週間を有給休暇または病欠(欠勤)を使った場合は懲役解雇できない
- 就業規則の懲戒規定に「無断欠席○日以上」等が解雇理由にある場合でも、この意思表示が相手方に達しないと効力が生じない(配達証明で文書を送るまたは公示送達する必要がある)
- 労働基準監督署長の認定が必要。(認定を受けずに、予告手当の支払なしに即時解雇した場合は労働基準法上の義務違反として罰則が適用される)
損害賠償同様に、懲役解雇も会社側にとってはなかなかハードルの高いものとなっているのが現状です。
また、会社側としてもたった一人の社員に費用や時間を費やすよりも、新たに社員を募集する方が効率が良いでしょう。
\ 最新情報を今すぐチェック /
※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。
疑問4.有給消化はどうすべきか?
有給休暇は労働者の雇入れ日から6か月継続し、全労働日の8割以上の日数に出勤した場合は必ず10日間の有給休暇をもらえる義務があります。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
– 労働基準法第三十九条
そのため、有給休暇を消化させないことは法律上違法です。
嫌がらせとして消化させないといった場合でも後日個人的に請求された際は企業側が損失する懸念もあります。素直に消化させるのがスムーズでしょう。
 オトシゴくん
オトシゴくん
ただし、会社側は有給申請された時季が業務の運営を妨げる場合は、他の時季に変更することが可能です。
「有給休暇請求に対する時季変更権」というもので、こちらも労働基準法で認められています。
とはいっても会社がこの時季変更を行うには下記の条件が伴います。
- 業務がどのように支障をきたすのかという客観的証明が必要
- 時季変更権は退職予定日を超えては不可能(有給申請者の請求が通る)
要は、いずれにせよ退職をすでに伝えているにも関わらず、有給休暇を拒否したり時季変更する事はできないわけですね。
\ 最新情報を今すぐチェック /
※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。
疑問5.未払い賃金はどうすべきか?
退職金・残業代・未払い給料など、未払い賃金も有給休暇同様、労働者が必ず取得できる権利です。
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を支払わなかった場合には、その使用者は労働基準法に違反することになるためです。(労働法第11条、第24条)
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
– 労働基準法第11条
ただし、一般的な退職代行業者(民間企業)は金銭面の交渉が民法上できないため、それを悪利用して支払わないこともできないわけではありません。
一方で弁護士が対応してきた場合は、当然交渉に必ず応じる必要があります。
もし応じずに支払わなかった場合は、訴訟に発展する懸念が見込まれるため、無難に応じておくのが良いでしょう。
とはいえ、いずれの場合も支払っておくのが無難でしょう。
金銭交渉ができない退職代行業者でも、後日退職者本人が労基署などを通じて請求するリスクがあるためです。
\ 最新情報を今すぐチェック /
※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。
結論:退職代行を使われた側(会社・企業など)は原則的に認めざるを得ない

以上の内容から、「退職代行を使われた側(会社・企業など)は原則的に認めざるを得ない」というのが当記事の結論となります。
退職代行を使われた腹いせに「損害賠償を請求したい」と思っても、現実的にはなかなかハードルが高く、時間や費用を考慮するとおすすめしません。
一人の労働者に固執するよりも、新たな人材を見つける方が効率よく会社側としても有益でしょう。
そのため労働者の雇用をどのように守っていくか、今後の反省点として次に活かすのが得策といえます。
\ 最新情報を今すぐチェック /
※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。
それでも迷惑?退職代行を使われた側が必ずしも被害者とは限らない
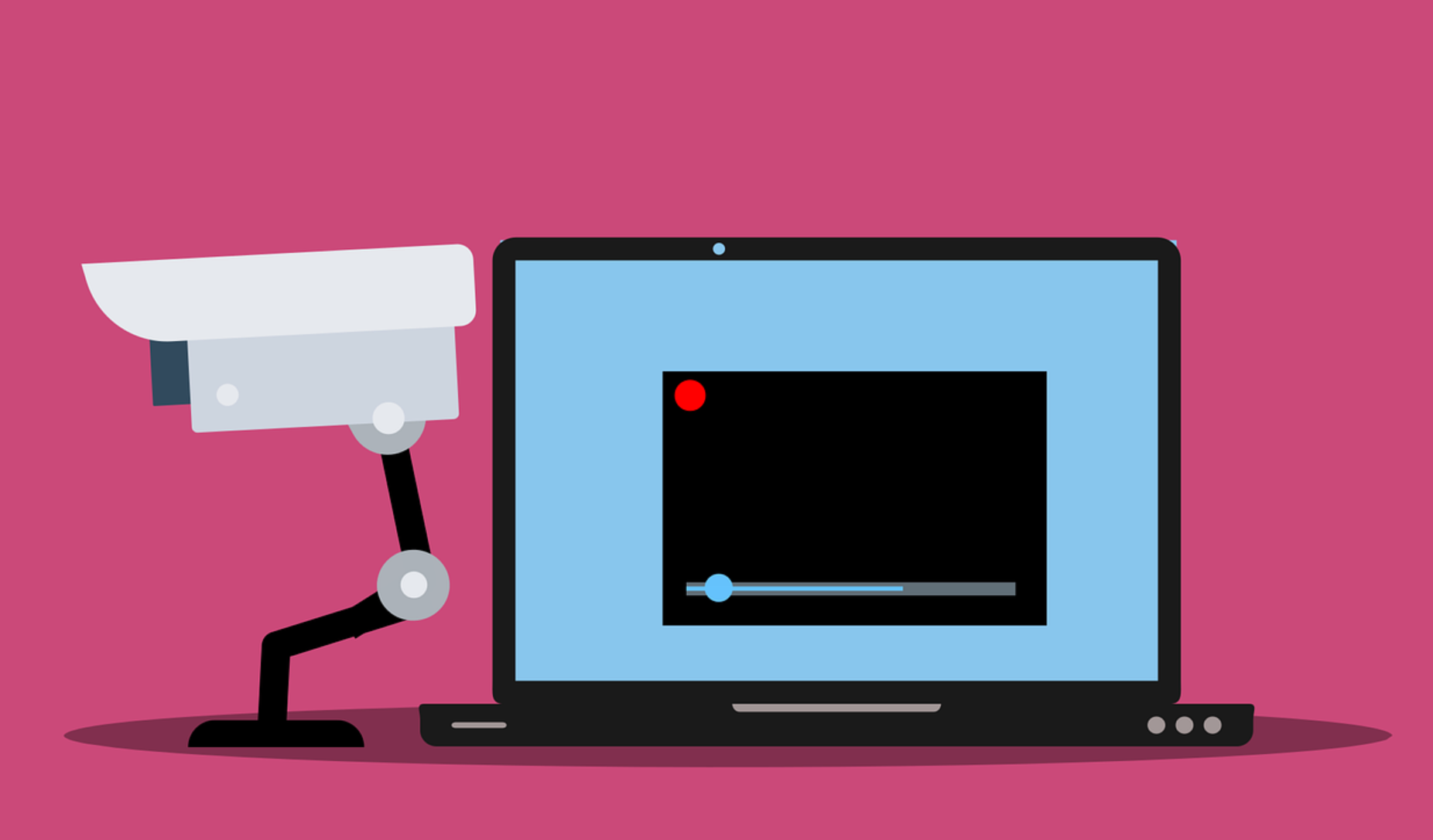
それでも「退職代行は迷惑」と思う場合は実際の声を参考にすると視野がさらに広がるかもしれません。
下記記事では、退職代行に対して反対派・賛成派の意見をそれぞれまとめ、両者の立場を比較しています。
 【暴露】退職代行はありえない?非常識?反対派の意見まとめ| どうなの?情けない?
【暴露】退職代行はありえない?非常識?反対派の意見まとめ| どうなの?情けない?
雇用側だけでなく労働者側の立場も考慮すると、退職代行サービスに対して別の視点が持てるでしょう。
なお、これから退職代行を検討しているという労働者であれば、下記リンクで最新情報を解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
\ 最新情報を今すぐチェック /
※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。
迷ったら!今月の人気(申込者数)ベスト3
 退職代行の教科書
退職代行の教科書